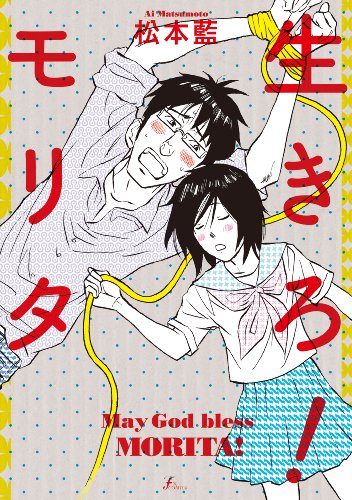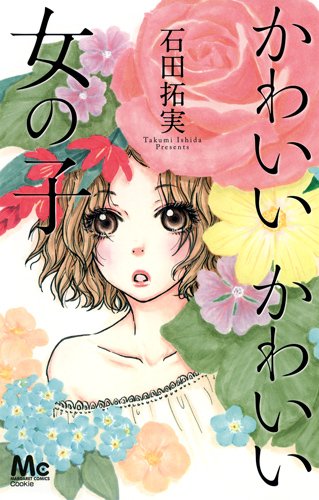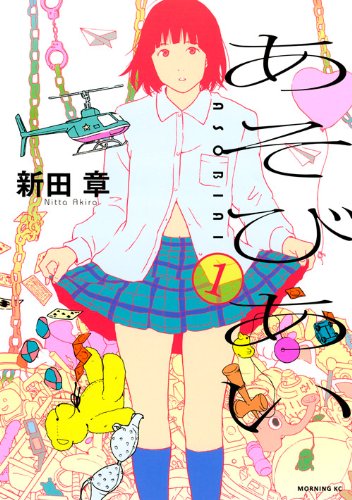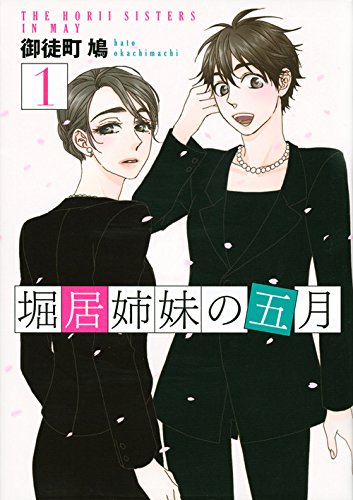自分で組み立てる民族楽器「ハーディーガーディー」がかっこいい!
ふと楽器がほしくなるときってありませんか?わたしはあります。
そんなとき「なにか良い楽器あるー?」と知人と話していたら「ハーディーガーディーが良いよ!!」と言われたのが先日のこと。ハーディーガーディーがなにか知らないまま調べると……実にすてき。しかも、つい最近『自分で組み立てるハーディーガーディー』が海外で発売されたようです。
その写真がこれ。
かっこいい!たまらない造形!
これがなんと、レーザー加工されたベニヤ板を自分で組み立てるキットで、完成したら実際に演奏できるという代物なのです。
ハーディーガーディーってどんな楽器?
ハーディーガーディーというのは、楽器本体に内蔵されている弓(にあたる円板)を取っ手を回して演奏するヴァイオリン。簡単に言うと『オルゴール型ヴァイオリン』です。
演奏動画を見てもらうのが早いです。どこかで聞いたことあるような音色だと思います!
自分で組み立てるハーディーガーディー?
そんなハーディーガーディーが、ベニヤ板の組み立てキットを作っているUGEARSという会社から発売されることになりました。

Kickstarのクラウドファンディング(UGEARS Hurdy-Gurdy: unique mechanical musical model - Kickstarter)を経て発売されて、日本では近日入荷らしいです!
値段は輸入されているぶん海外より少し高い11000円となります。(公式サイトはこちら:Hurdy-Gurdy - build your own fully fledged musical instrument by UGear | UGears | 木製の立体パズル)
これ発売した会社ってすごくない?!
今回『自分で組み立てるハーディーガーディー』を発売した UGEARSという会社ですが、時計や機関車、金庫なども発売しています。どれも実際に動くようです、すごい……。公式の写真や動画を紹介しますが、プラモデル好き、メカニカル好きなど多方面のひとにたまらない内容かと思います。これらは全部日本に輸入されています!
売り上げランキング: 207,679
売り上げランキング: 271,124
売り上げランキング: 216,687
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
簡単な紹介でしたが、以上となります。
機会があれば、最近手に入れた別の楽器の話もしたいと思います。ではまた。
特撮の書割っぽさは、思考実験らしさを強調するための手段である?
『シン・ゴジラ』見てきました。見てない人は見たほうがいいですね。
ゴジラシリーズは全く見たことないですし、特撮も見ない(映画だけでなくライダーも見てません)のですが、そんな中で見た『シン・ゴジラ』は「特撮とは何か」を得心させてくれるものでした。
特撮にはチープな印象を持っていました。きぐるみのゴジラがミニチュアを破壊するイメージ。なので、映画蓮明期であれば技術的な必然だったのでしょうけど、今の時代にわざわざチープなものを提示する(ie. ゴジラの新作が出る)必要はあるのか?という疑問がありました。
果たして映画がはじまると、最初から映像はチープな印象です。前情報を入れてなかったので、『シン・ゴジラ』がどこまでCGか分からないまま見始めましたが、CGは浮いて見えました。予算の問題か技術の問題かわからないけど、同時代の他の有名映画のCGに劣るように見えました。しかし、しかし、『シン・ゴジラ』を見進めて、少しチープ浮いて見えるCGや、果ては特撮である意義まで得心してしまいました。「特撮とは、SF的な思考実験を提示するものである。書割っぽさは思考実験らしさを強調するための一手段である」と考えました。
映画見てから他人の感想を漁って読みましたが、CGの質と役者の演技をマイナス評価している人はけっこう多いように見えました。なので「CGと演技に書割っぽさがある」という点までは、くどくどしい説明抜きに『シン・ゴジラ』を見た人に納得してもらえると考えます。この感想記事で言いたいのは「CGと演技の書割っぽさが、『シン・ゴジラ』の思考実験らしさを強調している」という点であり、そのためCGと演技の書割っぽさがわざとか予算の問題かわからないものの、今作の映画に表現的な側面でもわかちがたく組み込まれているという点です。
『シン・ゴジラ』の思考実験らしさを強調というのは、あれです。SFはSF的な現象の理由を読者が納得できるよう丁寧に説明することが必要かと思いますが、理由の説明を「これは特撮だからそういうものです、ゴジラだからそういうものです」として、その先にある結果を思考実験として観客に受け取らせるものだと見えました。書割っぽさが少ない(つまりCGも演技もすごく自然)であれば、「いくらなんでも怪獣は無い。なぜ怪獣を出した」と見てしまいそうですが、CGと演技の書割ぽっさがゴジラという現象の書割っぽさと結びついて、この映画はゴジラという現象の理由をリアルに書くのではなく、ゴジラという現象が起きたという思考実験を提示するからその先をリアルに考える、という映画に帰結していました。
■
浮世絵は造詣が浅いのだけれど、先日Bunkamuraの国芳と国貞の展示を先日見てきてすごくエロゲとの親和性を感じた。けどそういう言及してる人あまりいないかも?
浮世絵の有名な人の絵は名前も載っていてエロゲのOPのようだし、国芳の浮世絵は一枚絵風、国貞の浮世絵は立ち絵風。
なにより一番大きいのは、浮世絵の実寸がちょうどノートパソコンの画面サイズくらい(検索して調べたところ、浮世絵の基本サイズが17インチくらいらしい)という点。
さらに浮世絵は人物画が基本ななめ横を向いていて、エロゲの立ち絵を髣髴とさせる。
あと食事漫画がどんどん増えているし、上を向いて食べるものは食べ物を見せる構図、下を向いて食べるものは食べている人を見せる構図、として上向きと下向きで簡単にわかりやすく大別できるという話も、いつか書こうかしらと思いつつ年単位で時間経ってるかも。
書くとなったら上記の話はちゃんと書きます。
エロ漫画よりエロい!"性描写のある"おすすめ一般漫画ランキング【ベスト20】
エロい漫画が好きです。けど、いわゆる"エロ漫画"より、一般向けなのにエロい漫画が好きです。
"エロ漫画よりエロい一般漫画"という視点からまとめた記事は前例がないようなので、私が書きます。
ランキング形式でベスト20まであります。作家1人につき1作品縛りで選びました。
全作品傑作です。どうぞ!
20位 佐伯『BOX!』
19位 KUJIRA『ガールズノート』
18位 岸虎次郎『冗談だよ、バカだな』
17位 松本藍『生きろ!モリタ』
16位 石田拓実『かわいいかわいい女の子』
15位 新田章『あそびあい』
14位 山本中学『繋がる個体』
13位 渡辺ペコ『にこたま』
12位 犬上すくね『アパルトめいと』
11位 高野雀『低反発リビドー』
10位 武富智『C scene 武富智短編集』
9位 位置原光Z『アナーキー・イン・ザ・JK』
8位 日暮きのこ『喰う寝るふたり 住むふたり』
7位 阿仁谷ユイジ『阿仁谷ユイジ短編集 イタイほどかわいい』
6位 御徒町鳩『堀居姉妹の五月』
5位 雁須磨子『あたたかい肩』
4位 横槍メンゴ『クズの本懐』
3位 鳥飼茜『先生の白い嘘』
2位 シモダアサミ『mon*mon』
以上になります。
有名すぎる作品やエロと物語が水準に及ばない微妙な作品は削った上でのベスト20です。
エロはいいですよ!参考になればさいわいです。
4コマ漫画の1ページの構成について(特殊なコマのサイズの4コマ漫画)

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 (メディアファクトリーのコミックエッセイ)
- 作者: オーサ・イェークストロム
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/メディアファクトリー
- 発売日: 2015/03/06
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (16件) を見る
『北欧女子オーサが見つけた日本の不思議』がとても良い本です。何がいいって、作者ブログで連載している4コマを読んでいてもあらためて読みたいと思わせるほどに、情報が追加されているのです。

本全体でこのスタイルの4コマで、左側の一言(絵)があって読みでがあります。ここまでの本だとは思っていませんでした、うれしいびっくりです。
私は最近エッセイ漫画を読むようになりましたが、エッセイ漫画の4コマはふつうではないです。
“ふつうの4コマ漫画”というとこういう体裁だと思います。1ページに4コマが2本載っているのがふつうです。
(画像は『ゆゆ式』より)

ですが、エッセイ漫画では『ゆゆ式』みたいに“1ページに4コマが2本載っている”という体裁じゃないものが多いです。
「じゃあ、どういう体裁か?」と言われても、本やシリーズによって全然違います。手探りというか、ウェブで掲載された漫画が多くて、それを本にするにあたり出版社ごとに色々読みやすくなるよう工夫しているのでは?という状況に見えます。
そうした手探りにあって『北欧女子オーサが見つけた日本の不思議』が良い例だとしたら、『言うほどじゃないけど』は悪い例ではないでしょうか。

- 作者: 森もり子
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/中経出版
- 発売日: 2015/04/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (2件) を見る

この本は4コマのみではないのですが、例としてわかりやすいです。内容はさて置いても、1ページの情報量が少ないですね、悲しいです。見やすく作っているからこういう配置というわけでもないでしょう。
横長のコマなので1ページに2つ載せることができないサイズの漫画なわけですが、だからと言って中央にドンと載せてそれだけというのは、一枚絵ならそれでもいいんですが。
悪い例の次は、悪いとは言わないけど、言うなれば成功していない例でしょうか。『同居人の美少女がレズビアンだった件。』という漫画です。

同居人の美少女がレズビアンだった件。 (コミックエッセイの森)
- 作者: 小池みき,牧村朝子
- 出版社/メーカー: イースト・プレス
- 発売日: 2014/09/14
- メディア: コミック
- この商品を含むブログ (5件) を見る
1ページに4コマが2本という定着したフォーマットは、コマのサイズ的に情報量が多すぎず少な過ぎずの良いバランスになるから定着したのではないでしょうか。この漫画の横長の4コマは、1ページの情報量という点とコマ内の情報量のバランスのせいか、ふつうの1ページに4コマ2本の体裁の漫画より薄められているように感じました。

4コマのコマ割りについて書かれた記事はいくつもあるようでしたが、上に述べたようなサイズの違う4コマを扱った記事がなさそうなため、ちょっと参照性を高めるために書いておきました。落ちはありません。
エロクラに『フラテルニテ』を追加/「仰げば尊し」に関連して
エロゲのクラシックに『フラテルニテ』を追加しました。シューマン作曲「子供の情景 第1曲」と「仰げば尊し」です、公式サイトのムービーで確認できるので見ると良いかもしれません。
子供の情景について、原画家の人が「選曲過程は秘密」と書いておりそれ自体はさておき、原画家が選曲に関わっていたの?という点がやや興味深いです。
さて「仰げば尊し」について。
考えをまとめていないのですが、問題としたいのは「「仰げば尊し」が学校の情景を思い起こさせる曲として機能しているのか?」という点。
最近は「仰げば尊し」を卒業式で歌わないという話もある。そもそも「仰げば尊し」を歌う・歌ったのは小学校?中学校?高校?という点、つまりゲームで「仰げば尊し」を聞かせてどの場面を想起させたいのか。
エロゲ以外でも定番でエロゲでも結構使用されている「仰げば尊し」。製作者の年代で一般的だったから使用されているが、現在20才前後の人などでは一般的でない可能性は?
よしんば「仰げば尊し」が歌われていたとしても、「仰げば尊し」がどれほど印象的な曲であるのか?卒業式で歌われる曲というのはつまり卒業式でしか歌われない曲、卒業式で1度歌ったきりの曲と同義ではないのか?
学校生活において普段から耳にしていた音・音楽という観点からは、ウェストミンスターチャイムがエロゲその他で使用されるのは納得がいく。チャイムの音は毎日聞いていたことだろう。しかし「仰げば尊し」は、おそらく違う。
卒業式の歌として他にあげられる「蛍の光」についてはひとつの場面が思い浮かぶ。下校時の音楽、チャイム代わりとしての使用だ。学校でなく何かしらの営業終了の音楽としてもよく耳にするが、そういう日常的な使用がありそうだ。
そうやって考えて、では学校生活における日常的な音風景をBGMや効果音として使用するべきでは、と考えると、思い浮かぶのは休み時間の雑踏音というか騒ぎ立てるような声だろうか。しかし確かに、子供(小学生、中学生、高校生)が大人数しゃべっており、そこに大人の声など他の騒音(電車の音など)が混じっていないという雑音は、学校以外ではあまりない。
音楽を使用したいとなると、やはり「仰げば尊し」が出てきてしまうのはしょうがないところかもしれないが、「仰げば尊し」に近い曲調であれば他の曲でも意外と代替可能なのではという印象がある。…「ふるさと」とか?
こういう意味でのもうひとつの定番は国歌だと思うけれど、使用例を見たことがないのは自主規制だろうか、それとも普通にだめなのだろうか。替え歌などでそれ自体に矛先を向けるのでなければ、あまり問題があるようには思えないし、色々な文脈とか曲調とか踏まえても使いどころの多い曲ではあるはずだが。
あとは「さくら」。これの使用例が少ないのもちょっともったいない感じ。きれいどころの曲としては良かろうに。
こうして考えていくと「夕焼け小焼け」と「花いちもんめ」を使用している『R.U.R.U.R』の目の付け所がすばらしいように思える。それと『はるまで、くるる。』の「春よ来い」。耳馴染みがあって、小学校あたりを想起させる選曲としては、これらのほうが個人的にはしっくりくる。あとは「通りゃんせ」とかそういうのに向いてる曲だろうに。あと「グリーングリーン」。
ひとりで複数の箸を使い分けるとすばらしい
ひとりで晩御飯を食べているとき、間違えて取り箸で食べたその瞬間に天啓がきました。ひとりが複数の箸を使い分けると食事の可能性がより広がる。
取り箸は別にして、箸はひとり一膳。それがふつう。しかし、箸をひとりで使い分けるという可能性があることに気づいた。
ナイフ・フォークは使い分ける。皿の内容で大きさや刃の入り方などの異なるものを使い分ける、するとおいしく食べられる。マナーの問題かもしれないが。
箸は、ひとり一膳、取り替えない、使い分けない。よしんば使い分けても、それは食事ごとに変わるくらいで、洋食のコースを食べるようには使い分けない。しかし、しかし、使い分けてもいいじゃないか。考えてみたが、箸を複数使い分けることは、マナー的には問題ない。例えば和食のコースでだって、皿ごとに箸を取り替えるということは忌避感があるわけでもない。
箸を使い分けるとどうなるか、食事がおいしくなる。
自身で気づいたことでは、例えば硬い箸のほうが食材の触感を味わえる。それは口に入れる前、箸でとらえた時点での話である。逆にやわらかい箸のほうが、口当たりというか、口に運んだときの感触がやさしい。つまり、触感が大事な料理では塗り箸を使い、ご飯などやわらかいものでは塗りの無い木箸をなどはありうるだろう。木の素材で使い分ければ可能性は広いし、箸は竹も金属もある。
そもそも、箸を汚さないで食べるという考え方自体もここで考えるべきところであった。汚れるなら複数の箸を使えば良い話だ。それは今なら逆にマナーとして定着してしかるべきほどの話だ。食器を使いまわすことは望ましくない、皿は使いまわさない、ならばその皿をおいしく食べるためには食器も変えるべきであった。
料理に合わせて皿を変えるのは当たり前のあたりまえだ。取り合わせも変わる。
「お好みで〜の塩をつけてお召し上がりください」というのがあるのだから「こちらはお好みで〜の箸をお使いください。少し固めがお好きであれば〜の箸ですとよりおいしくお召し上がりいただけます」とかあっても良い。
料理自体がおいしいかどうかとは別に、根本的な土台だがマナーとしてだめでもないという箸はひとり一膳というところを変えることで、特に外食なんかだと一段高級でおいしいものにできるはず。
発想自体がたぶん無いから一読なるほどと書けた気はしないが、つまり「一度の食事の異なる料理で箸を使い分けるべき」という話。ナイフとフォークでは料理で使い分けるのがふつうだが、箸でそれをやっているのは寡聞にして聞かない、少なくともそこら辺の料理屋である話ではない。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21しかし箸も多様、むしろナイフ・フォークより材質がばらけるぶん多様じゃないかしら。多様であるから、料理との取り合わせで料理の味は変わる。塗りのあるなし、木の種類、あるいは竹、金属、箸の持ち手の意匠、箸先の細工。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21家庭で料理ごとに使い分けるとさすがに大変なことになってしまうが、こと料理屋ではそんなことはないはず。一皿ひとさら料理を提供するようなある程度以上に高級な和食なら、料理によって箸を取り替える・料理に合わせる使い分けさせる、というのは話としておかしくない。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21マナー的にも、箸が新しくなるわけだし、発想としておどろいたとしても殊更忌避感につながることはないはず。むしろ箸先が汚れているのが何も言わずとも変えてもらえるなら、サービスとしてより良いのではないか。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21例えば味噌の料理が出た、どうしても箸先は汚れやすい。その料理はこの塗り箸で、次の薫物は塗り箸より滑りにくい無垢の木箸でどうぞ、というのはまったく正しいはず。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21そう、海外の料理の良いところを取り入れるのであれば、テーブルに箸が皿の数だけ並べるという発想だってあって良かった。使い分けたほうが料理はおいしい、高級な食事は無理なく室が上がりより高級になる。こだわらないのもまた普通の範囲でおかしくないが、こだわるなら変えることで良くなるのだ。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21弁当や惣菜を買うと割り箸が付く場合がある。そこではひとり一膳。そのほか箸マナーが自分の箸はひとつで他の箸が混ざるべきではないという文脈があり、そのような流れの中では一人が箸を次々と取り替えて使うということは思いつきにくかったであろう。しかし別の箸を複数使うことはマナーに違反しない
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21弁当や惣菜を買うと割り箸が付く場合がある。そこではひとり一膳。そのほか箸マナーが自分の箸はひとつで他の箸が混ざるべきではないという文脈があり、そのような流れの中では一人が箸を次々と取り替えて使うということは思いつきにくかったであろう。しかし別の箸を複数使うことはマナーに違反しない
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21ここで、イメージするのはあくまで高級よりな食事の場であることに注意したい。割り箸の大量使用が環境破壊云々という話も、箸はひとり一膳という暗黙の文脈に拍車をかけたはず。別に割り箸を一度に3膳使ってもいいが、それは恩恵が少ない例である。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21同じ(規格の)箸を複数使っても、それは箸が汚れる云々にしか影響しない。ならばそれは乱用のイメージがついてくる。ここで想定しているのは、料理と皿を合わせて、細かいことにもちょっとこだわっていますよ、というような食事である。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21料理にこだわり、皿にこだわり、内装にこだわるのなら、そこにもう一つ、食器というこだわれる部分があったのだ。箸にもこだわると良い、そうすることでこだわりの料理はより一段こだわり度を増し高級になる。単に高い食材だとか高い食器や内装で高級になっていくよりは、気の利いたこだわりが良い。
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21そうしたちょっと良いサービスとして、箸にこだわるという部分がありえる、という話だ。ほんとうに、そこら辺の中華屋でも箸とレンゲは使い分ける、すがきやのスプーンは有名、あまりに安くささくれだった割り箸だと食事がおいしくない。色々あるんだから、ここにこだわるのはもっと一般化してよかった
— mp_f_pp (@mp_f_pp) 2014, 6月 21


![Ugears 機関車モデル 自分で組み立てて、ゴム動力で動く3Dパズル インテリアにも最適 [並行輸入品]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41DikUusjBL.jpg)